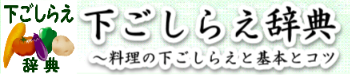料理の下ごしらえと基本とコツ
揚げ油の適温は揚げるものによって違います。油用の温度計がなくても天ぷらやフライ、唐揚げの衣クズを使えば揚げ油の温度が見分けられます。
えび(海老)の洗い方、殻の剥き方、背わたの取り方などの下ごしらえ
エビの洗い方、殻付きエビの背わたの取り方、殻なし海老の背わたの取り方、殻つき海老のゆで方、殻の剥き方、加熱したとき曲がらない用意するには?
簡単ミートソースの作り方(スパゲティミートソース)失敗なしです
トマトの水煮缶を使うのでトマトの皮むきもなく手軽にできます。面倒なのは、野菜のみじん切りくらいです。失敗なしの簡単ミートソースの作り方です。
キッチンバサミや皮むき器(ピーラー)・スライサーの安全な洗い方
キッチンバサミや皮むき器(ピーラー)・スライサーの洗い方です。使い古しの歯ブラシを利用すると安全に洗えます。キッチンバサミや皮むき器(ピーラー)・スライサーは刃物なので扱い方に気を付けないと手を切るなどの怪我をしてしまいます。
日本酒は熱燗、ぬるめの燗、それとも冷酒派?酒の燗には、温燗(ぬるかん)、上燗(じょうかん)、熱燗(あつかん)とあります。徳利に入れて日本酒の燗をする方法です。美味しい熱燗の作り方です。
手についた魚の生臭さってしつこく取れません。まな板についた生臭さも取れにくいし、焼き魚だとグリルはベトベト、臭い。お茶を使った調理前の臭み消しの方法です。
唐辛子のことを九州では”胡椒(こしょう)”ともいいます。 柚子胡椒(ゆずこしょう)は、冷奴、そうめんの薬味、刺身、豚汁や味噌汁に、鍋物の薬…
ネギ(白ねぎ・深ねぎ・根深ねぎ・長ねぎ)の食べられるところと利用法
ネギ(白ネギ・深ネギ・根深ネギ・長ネギ)の「食べられるところ」と「食べられないところ」と「利用法」です。ネギは無駄なく使える野菜なんです。
栗の皮(鬼皮・渋皮)のむき方とあく抜き。包丁・熱湯・ボウルでOK!
栗の鬼皮は堅くて剥くのにコツがあります。包丁と熱湯とボウルを使っての栗の鬼皮と渋皮のむき方と、水にさらすまでの下ごしらえ、ゆで栗のゆで方、栗の保存方法について、です。
「海水程度の塩水」とは、海水とほぼ同じの3%くらいの塩分の水のことです。つまり、水1リットルに対して塩30gです。覚え方は、計量カップ1に対して塩は小さじ・・・
絹さや・さやえんどうのガクや筋は調理前に取っておきます。火を通しすぎると色も悪く、歯ごたえ、味も悪くなるので下ゆでをさっとしてから使います。
かぼちゃ(南瓜)の下ごしらえ~かぼちゃの切り方、種とワタの取り方
日本かぼちゃ、西洋カボチャとありますが、主流は甘みがあってホクホクした西洋カボチャです。かぼちゃは固いので切る時は気をつけてください。かぼちゃの切り方、種とワタの取り方など、です。
とうもろこしの茹で方~水から・熱湯から、薄皮付き・薄皮なし?塩加減は?
とうもろこしは薄皮付きのまま茹でるのか、薄皮を剥いでから茹でるのか?水から茹でるか、沸騰して茹でるのか、電子レンジで茹でる方法、ヒゲはどの段階で取るのか、などご案内します。
まな板には木製、プラスチック製といろいろありますが、生で食べるものも切るので、いつも清潔にしておきたいものですね。重曹や酢、塩を使ったお手入れ方法です。
「野菜をゆでる」「野菜の下ゆでをする」ときに、「水からゆでる」のか、「熱湯からゆでる」のか?硬い部分と柔らかい部分を均一にゆでるにはどうしたらいいか?ゆでたあと「水に浸す」か、「浸さない」か?迷いませんか?
自家製梅干の作り方~塩分20%の昔ながらの漬け方はカビない!
梅は古くから三毒(水の毒・血の毒・食物の毒)を断ち、其の日の難を逃れると言われてきました。 梅にはクエン酸をはじめとする有機酸などが多く含…
芋茎(ずいき)は、サトイモやハスイモなどの葉茎で、芋がらは、ずいきの皮を剥いて乾燥させたものです。ずいきのあく抜き、芋がらのあく抜きと戻し方です。
安納芋(さつまいも)で栗なしの「芋きんとん」の作り方です。クチナシを入れなくても鮮やかな黄金色のきんとんができます。栗の甘露煮のシロップを入れないので自然な甘さですっきりとした味わいです。
ジャガイモの皮を使ってステンレスのシンクを磨くとピカピカにります。ジャガイモに含まれるサポニンには界面活性剤の働きがあるので洗剤代わりになるそうです。
雑炊を作るとご飯がベタベタになりませんか?せっかくおいしいダシで雑炊を作ってもベタベタしていてはおいしくないです。長く煮過ぎないのも大切ですが、他にもコツがいくつかあります。
キウイフルーツには、ビタミンCやビタミンEが豊富で強い抗酸化力を有しており、食物繊維やカリウム、ミネラルも豊富に含まれています。キウイフルーツの種類と選び方をご紹介します。
ジャガイモの代表品種の男爵とメークイン。ジャガイモの選び方、下ごしらえです。ジャガイモの芽にはソラニンという毒素を含んでいますので取り除き、切ったあとのはアク抜きが必要です。
なめこの洗い方・株なめこの石づきの取り方・消費期限の見分け方
袋詰めのなめこは洗う?洗わない?ヌメリは?株なめこの石づきの落とし方や洗い方、賞味期限や痛みの見分け方、調理別下ごしらえの方法です。
葉が薄く切り込みが多く根元が赤い東洋種と、葉が厚く丸みを帯びている西洋種の2種類があります。ほうれん草の洗い方、ゆで方・ゆで時間、あく抜きなどの下ごしらえの方法です。
エビフライなどの海老料理を作ったときなどに、海老の頭が残ったときは、どうしていますか?捨ててはもったいないです。海老の頭や殻でおいしいダシやスープをとりましょう。
椎茸(生椎茸)の汚れの取り方、洗う?洗わない?軸は食べられる!
生しいたけやマッシュールーム・松茸などのきのこ類はかさの裏側にうまみがあります。きのこは水洗いをしたら、水と一緒にうまみも流されてしまいます。
ピーマンはトウガラシの品種の一つで、赤ピーマンは緑のピーマンを完熟させたものです。ピーマンの下ごしらえや皮のむき方と、ヘタ以外は丸ごと食べられる美味しい調理法もぜひ!
りんごの芯抜きを買ったら焼きりんごの作り方が載っていました。ちょっと手間をかけた作り方だったのでご紹介します。少しアレンジしています。材料の分量は記載されていなかったので、我が家好みで。
慈姑(くわい)の下ごしらえ(あく抜き)と慈姑の含め煮の作り方
お正月のおせち料理に入っている縁起物の料理「慈姑の含め煮」。「慈姑」のあく抜き・下ごしらえの方と慈姑の含め煮の作り方レシピです。
手作りチキンカレーのレシピ~自家製カレールゥで作るチキンカレー
カレーをカレールゥから作ってみませんか?市販されているカレールーは種類も豊富で各社それぞれおいしいですが、ルゥから作る自家製カレーもよいものです。チキンカレーです。
さわやかな梅の香りがする梅味噌ドレッシングを作ってみませんか?青梅でも黄色に色づいた完熟梅でも作れます。味噌の種類は、麦味噌、米味噌、あわせ味噌どれでもいいですし、ブレンドしてもOK!
鉄製のフライパンや中華鍋・鉄鍋などの鉄製の鍋類は使い方や手入れの方法を間違うと錆びてしまい使えなくなってしまいます。使い方の注意点と手入れの方法です。
鮮度が落ちやすく、あまり保存はきかないので購入したら早めに料理してください。ブロッコリーは捨てるところの少ない野菜です。無駄なく食べれる下ごしらえの方法をご説明します。
「塩味の炊き込みご飯の塩加減について」です。グリンピースご飯、菜めし、栗ご飯、大根の葉のご飯・・・など、塩味の炊き込みご飯がおいしく炊ける塩加減は・・・
100円くらいで売っている甘栗で栗ご飯を炊いてみました。甘栗がもっちりとして美味しいです。あっさり塩味で雑穀と一緒に炊きましたら美味しかったのでご紹介します。
四季を通じて店頭に並んでいるキャベツですが、旬はいつ?芯は食べられる?千切りキャベツは、葉を洗ってから切る?切ってから洗う?キャベツの葉を上手に剥がすコツ、洗い方などの下ごしらえの方法をご紹介します。
オクラは煮物など直接煮たり、生食でも、茹でたりして食べます。オクラのうぶ毛はきれいに取り除きます。洗い方のコツと、うぶ毛の取り方、下ゆで・下ごしらえについてです。
かんぴょうの戻し方~漂白かんぴょうと無漂白かんぴょうの下ごしらえ
かんぴょうは水で戻して柔らかくしてから料理しますが、「漂白かんぴょう」と「無漂白かんぴょう」では戻し方の手順に違いがあります。
電子レンジを使った後にすぐに汚れをふき取るのが良いのですが、調理中はなかなかできないものです。汚れが残ってしまった時の落とし方と電子レンジの庫内のニオイの消し方です。
あずき(小豆)は他の豆に比べると皮が破れて煮崩れしやすいので、ほかの乾燥豆のように一晩水に浸すことなく、いきなり水から茹でます。あずき(小豆)のゆで方・煮方、下ごしらえのご案内です。
おはぎ(お萩)とぼたもち(牡丹餅)はよく似ています。どちらも突いたもち米にあんこ(粒あん・こしあん)をくるんだ和菓子です。おはぎ・ぼたもちを作ってみませんか?
米の収穫は、品種や産地、気候などで多少の違いはありますが、7~10月頃です。 食品表示基準によると、「新米」と表示できるのは、収穫後、その年の12月31日までに包装された玄米・精米とされています。
塩蔵わかめ(塩わかめ)・乾燥わかめは、水に漬けて塩抜きあるいは戻してから料理します。生わかめの下ごしらえ、塩わかめ・乾燥わかめのもどし方をご説明します。
薄塩で作る自家製ベーコンの作り方です。通常は4日~1週間くらい下味をつけておき、いぶした後熟成せるのに数日かけて作りますが、少しスピードアップした作り方でしています。
アルコール不使用のマロングラッセの作り方です。アルコール入りのお菓子が苦手な方やお子さんにもおすすです。本格的なマロングラッセと違い、日にちも手間もかかりません!出来立ての温かいときでも、冷めてもおいしいです。
当たり鉢とは、すり鉢のこと。 「する」という言葉を嫌って「当たる」と呼んだ。 すり鉢の忌み詞(ことば)。 当たり木(あたりぎ・すりこ木の忌み詞)とセットで使います。
土鍋の使い始めと取り扱い方~お粥で目止め、ひび割れ防止と臭い消し
土鍋の使い始めは、鍋の強度を高め、鍋のあく抜きやどな錬特有の臭い消しをするために目止めをします。目止めの方法や土鍋の取り扱い方法、ヒビが入ってしまったっときの対処方法です。
味噌は、ボコボコ煮立てたり、長時間煮すぎてはまずくなるので、具を入れるタイミングは具材によって違います。味噌が先か、具が先か、根菜類、葉物・・・タイミングはこの記事でどうぞ!
数の子の下ごしらえ(塩抜き・薄皮むき)から味付け、漬け汁の再利用法
数の子の塩抜き(下ごしらえ)から味付け、数の子の漬け汁の再利用法です。塩数の子の塩抜きは、ほんのり塩味が残る程度にすると仕上がりが美味しくなります。塩抜きに時間がかかりますので、薄皮を取れる時間に合わせて塩抜きを始めてください。
こんにゃくのあく抜き・下ゆでの方法~糸こんにゃく・板こんにゃく
「板コンニャク」(しらたき)「糸コンニャク」「玉コンニャク」「キンピラこんにゃく」などがあります。こんにゃくのあく抜きと下ゆでの方法です。
胡麻(ごま)の炒り方、洗いごま・生ごま・炒りごま・すりごまの違い
胡麻の美味しい炒りかたです。「洗いごま」「生ごま」は煎ってから使います。「炒りごま」はそのままでも使えますが、軽く煎ると香ばしさが出ます。
カリフラワーの洗い方・ゆで方などの下ごしらえの方法です。酢や小麦粉を使ってカリフラワーを白くキレイにゆでるコツもご紹介しています。
排水口は汚れやすいので、こまめに掃除しないとヌメリが発生して台所が不衛生になってしまいます。重曹とクエン酸を使っての排水口の掃除をご紹介します。
「田作り」は田畑の肥料として使われていた事から、別名「五万米(ごまめ)」とも呼ばれています。出来合いが販売されますが、自分でももちろん作れます。五穀豊穣を願って、どうぞ!
福岡では、お雑煮の青菜に「かつお菜」という野菜を使います。漢字では「勝男菜」で、縁起が良いということでお正月の博多雑煮に添えます。かつお菜のゆで方・下ごしらえの方法です。
生椎茸がたくさん手に入ったときや、使い切れなかった生椎茸は、自家製干し椎茸にしませんか?生椎茸は日が経つと裏側が赤く変色して傷んでしまうので、痛む前に干し椎茸にしましょう。生椎茸より天日で干した椎茸は栄養価もぐんとUPするそうです。
しじみ・しじみ貝(シジミ、蜆貝)味噌汁、お吸い物もとっても美味しいシジミ汁。あさり貝に比べて小さなシジミですが、栄養はたっぷり!シジミの砂抜き方法と、保存方法、シジミの身は食べるか食べないか?しじみの味噌汁、お吸い物のマナーの食べ方とは?
お中元やお歳暮で塊のハムなどを頂くことがあるかと思います。 塊のハム、美味しいです。 ですが、塊のハムやベーコン、ソーセージなどは、一回…
高温多湿の梅雨時期は、乾物類は湿気を帯びたり、悪くするとカビが生えたりします。なので梅雨前に、昆布、干し椎茸(干しシイタケ)、かんぴょう、高野豆腐、切り干し大根、ひじき、麩(ふ)、鰹節、干し竹の子(干し筍)などの乾物類は料理して使い切ってしまいましょう。
料理本やレシピには調味料などの計り方に「ひとつまみ」「ひとつかみ」「適量」とか「少々」などの微妙な表現があります。この微妙な計り方をご説明します。 。
おせち料理に欠かせない黒豆煮をご家庭で作ってみませんか?黒豆(乾燥)の戻し方・下ごしらえと黒豆煮の作り方です。重曹を入れなくても美味しく作れます。
まいたけ(舞茸)の汚れの取り方、美味しい切り方。生食はダメ!
舞茸の香りはとても強いので、他の食材の風味を消してしまわないよう、量を加減して使ってください。舞茸の洗い方(洗う?)、切り方などの下ごしらえです。
高野豆腐(こうやとうふ)は豆腐を凍らせて乾燥させたもので、凍り豆腐、しみ豆腐ともいいます。ぬるま湯で戻してから料理をします。もどし方の説明です。
醤油の種類と違いと使い分け~薄口醤油・濃口醤油・甘口醤油など
JAS規格で定められている「濃口醤油・薄口醤油(淡口醤油)・溜醤油・再仕込醤油・白醤油」の5種類の違いと使い分け、九州の甘口醤油・刺身醤油ついてご紹介します。
ぜんざいの作り方~2025年の鏡開きに「ぜんざい」、夏は「冷やしぜんざい」
2024年の鏡開きは1月11日です。鏡開きのお餅でぜんざいを作りませんか?砂糖の量は一般的な量でご紹介していますが、お好みで増減させてください。我が家のぜんざいは、かなり砂糖を控えて作っています。
喉に良いといわれる金柑。金柑の焼酎煮は冷蔵庫に入れて置けば1年くらいは保存できます。 じっくり煮るので焼酎のアルコール分は蒸発しますので、子供も食べられます。
和からしはぬるま湯で練ると辛い!旨い!和辛子と洋カラシの違い
からしは、アブラナ科のカラシナの種子から作られる香辛料で「和からし」と「洋からし」に分けられます。「和からし」(粉からし)を辛く、美味しく練る方法(和からしの作り方)です。
かぼちゃのスープの作り方~ミキサー・裏ごし、玉ねぎなしの簡単レシピ
パンプキンスープ(かぼちゃのスープ)の作り方レシピです。面倒な裏ごしなし、玉ねぎなしで、かぼちゃの食感があるスープです。
「重曹または木灰使用の昔ながらのあく抜き方法」と、「塩と小麦粉使用で短時間で出来るあく抜き方法」の2種類と保存方法をご紹介します。
ネギ・青ネギ(小ネギ・万能ねぎ)は根っこ以外は全て食べられます。青ネギの扱い方、一度買えばしばらくネギを買わなくて良いおトクな再生栽培をご案内します。
柚子:丸ごと湯船に入れてゆず湯に、皮は薬味、果汁は風味付け、種は美肌化粧水
皮は刻んで薬味に、果汁は絞って風味付けに使います。種は日本酒や焼酎に漬け込むことで美肌化粧水になります。冬至に湯船に柚子を浮かべた「ゆず湯」で身体を温めましょう。無駄なく使える柚子についてご案内します。
菜の花はゆですぎるとクタクタになってしまいます。水に浸けると水っぽくなるのでゆでたあと菜の花は水にさらしません。菜の花のゆで方のコツをまとめました。
松茸の独特の香りを逃さないように下ごしらえをします。松茸の洗い方(基本洗わない)、香り良く切る方法、虫食い松茸の対処方法、保存方法について、です。
七草粥の作り方~土鍋での作り方、炊飯器での作り方。2025年の健康祈願
新春の1月7日の朝に春の七草をお粥にして食べると「邪気を祓い、万病を除く」という言い伝えがあります。七草粥(ななくさがゆ)を土鍋で炊く方法と炊飯器で炊く方法をご案内します。

2024年の鏡開きは1月11日です。鏡開きのお餅でぜんざいを作りませんか?砂糖の量は一般的な量でご紹介していますが、お好みで増減させてください。我が家のぜんざいは、かなり砂糖を控えて作っています。

新春の1月7日の朝に春の七草をお粥にして食べると「邪気を祓い、万病を除く」という言い伝えがあります。七草粥(ななくさがゆ)を土鍋で炊く方法と炊飯器で炊く方法をご案内します。

喉に良いといわれる金柑。金柑の焼酎煮は冷蔵庫に入れて置けば1年くらいは保存できます。 じっくり煮るので焼酎のアルコール分は蒸発しますので、子供も食べられます。

おせち料理に欠かせない黒豆煮をご家庭で作ってみませんか?黒豆(乾燥)の戻し方・下ごしらえと黒豆煮の作り方です。重曹を入れなくても美味しく作れます。

数の子の塩抜き(下ごしらえ)から味付け、数の子の漬け汁の再利用法です。塩数の子の塩抜きは、ほんのり塩味が残る程度にすると仕上がりが美味しくなります。塩抜きに時間がかかりますので、薄皮を取れる時間に合わせて塩抜きを始めてください。

お正月料理の定番の栗きんとんの作り方レシピです。市販のものと違って甘さを調節できるのでおすすめです。クチナシの実を使えば色鮮やかに仕上がります。
スポンサードリンク

超簡単な海老フライのつくり方です。卵と小麦粉を使わず、油で揚げず、グリルで焼く海老フライです。お弁当のおかずにぜひ!

お豆腐は栄養満点! 豆腐3パック100円などで買っておくと、1個くらい賞味期限…

カリカリらっきょうの甘酢漬けの漬け方(らっきょのつけ方)です。 私は、下漬け(…

厚揚げも油揚(薄揚げ)げも、豆腐を揚げたものですが厚さが違います。 焼くとき以外はどちらも油抜きをしてから料理します。

新ジャガイモ(新馬鈴薯)は皮付きでそのままでもOK!皮をむくときは包丁ではない方が剥きやすいです。
![]()
ようこそ!
『下ごしらえ辞典』
~料理の下ごしらえと基本とコツ~へ
iPhoneアプリ「フード/ドリンク」無料カテゴリで発表2日で4位、無料アプリ総合ランキング最高135位!の『下ごしらえ辞典』がサイトになりました。
アプリよりも種類を多く増やして行きます。
スマホがあれば、どこでも簡単に調べれるようにわかりやすく紹介していきますのでよろしくお願いします。
掲載されている記事・画像などの無断コピー・無断転載を固く禁止します。
まとめサイトや知恵袋等でご紹介くださる場合は、必ず参照元である当サイト名を明記してリンクをして下さい。
Copyright © 下ごしらえ辞典 〜料理の下ごしらえと基本とコツ All rights reserved.