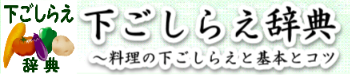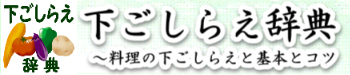枝豆のうぶ毛の取り方、おいしい茹で方

枝豆(えだまめ)
夏!ビールのおつまみにぴったりです。
ほかに、サラダや和え物、煮物などに。
枝豆の旬

枝豆(えだまめ)は、大豆が未成熟で青いうちに収穫した豆のことです。
枝豆の旬は6~9月、夏野菜です。
「塩ゆで枝豆」の口当たりが良くなるコツ!

枝豆の鞘全体についている「うぶ毛」を茹でる前に取り除いておくと、口当たりが良くなります。
この「うぶ毛」、水洗いだけでは、なかなか取れません。
「塩ゆで枝豆」の下処理(下ごしらえ)
- 大きなすり鉢に、洗って水切りをした枝豆を入れ、やや多めに塩をふります。
- 枝豆をすり鉢の溝にこすりつけるようにしながら5分ほど力を入れてもんで鞘についている「うぶ毛」を取ります。
塩は付けたままゆでます(枝豆のゆで方へ↓)。
大きなすり鉢がなければボウルで代用してください。
でも、すり鉢の凹凸がいいんですけど・・・。
すり鉢に入れる前に鞘の両端をハサミで切っておくと、鞘の中の豆に塩気がほどよく染みて、美味しく茹で上がります。

枝豆のゆで方

- たっぷりの湯を沸騰させ、「うぶ毛」取りをした塩が付いたままの枝豆を入れます。
◆ゆで加減は・・・
枝豆は、ゆで上がり時間がわりと早いので、ゆで過ぎになりやすいので気をつけます。
途中何度か食べてみてゆで加減を確認しながらゆでたほうがいいです。
熱いので口を火傷しないように気をつけてください。 - ゆで上がった枝豆はザルに広げて全体に塩を軽くまぶし冷やします。
◆冷やし方は、
ザルに広げた枝豆を冷水にさっとくぐらせ「あら熱」を取る。
または、
ザルに広げた枝豆をうちわであおぎ「あら熱」を取る。冷やし方で、ゆであがりの色、歯ごたえ、風味が決まります。
水を使わないほうが、水っぽくなくていいですが、うちわであおぐときは余熱でゆで過ぎにならないようにします。
食べてみて塩味が足りないときは、パラパラと塩を振りかけて調整してください。
すぐ食べても、冷蔵庫で冷やして食べても! お好みでどうぞ。